乳癌には様々な種類や定義がありますが、多くの場合、ミルクの管(乳管)から生じる「乳管癌」を指します。
乳管は乳房内にアリの巣のように張り巡らされており、乳管癌はその1本1本の管の内側から生じます。
浸潤性乳癌と非浸潤性乳癌
乳管の内側から生じた癌は、大きくなるにつれて管を押し広げつつ乳管に沿って広がっていくタイプと、管の壁をすぐに突き破って大きくなるタイプに分かれます。
管の中に癌が収まっているタイプを「非浸潤性乳癌」、略して「非浸潤癌」。管の外に出てしまったものを「浸潤性乳癌」、略して「浸潤癌」と呼びます。
多くの浸潤癌は非浸潤癌成分も含まれており、少しでも管の外に出ている部分があれば浸潤癌とされます。
浸潤癌と非浸潤癌の治療の違い
「浸潤癌」は乳管の外にでて、まわりの組織を壊しながら大きくなっていくわけですが、乳管の外には血管やリンパ管など、全身とつながっている管がたくさん走っています。癌細胞がその管に紛れ込んでしまうと、血液やリンパ液に混じって癌細胞が全身を巡ってしまう可能性があります。
全身を巡った癌細胞が、肝臓や、肺、脳、骨などで芽を出し、しこりとなったものを「転移」と呼びます。
そのため、「浸潤癌」は、乳房内にできたしこりをとるだけでは全身に巡ってしまっている ”かもしれない” 癌細胞をやっつけることができません。「浸潤癌」と診断された場合は、手術でしこりを取ってしまうだけではなく、点滴や飲み薬による治療を行う必要があります。このように全身にめぐってしまっている ”かもしれない” 癌細胞に対して行う治療を「全身治療」と呼びます。
一方、「非浸潤癌」では、乳管の中に癌細胞が収まっているため、理論上は全身に癌細胞が巡ることはありません。つまり、おおもとのしこり(非浸潤癌は乳管の内側を這って広がるため、しこりを作らず、網状に広がっている場合があります)を手術で取り切れさえすれば、理論上再発や転移を起こすことはありません。
※ただし、検査には限界があるため、非浸潤癌と診断された方の中には、ごく一部乳管の外に出ている部分を見つけることができず、1%程度の確率で将来転移や再発が起きるといわれています。
全身治療とサブタイプについて
では、「浸潤癌」と診断されたら一体どんな全身治療が行われるのでしょうか。
それは、乳癌の性質(サブタイプ)によって変わります。
乳癌のサブタイプは、女性ホルモンをエサにするかどうかで2パターン、HER2(ハーツー)タンパクと呼ばれる、アンテナのようなものを持っているかどうかで2パターン、合計2×2の4種類に分かれます。
それぞれのタイプは以下のように呼ばれます。
①女性ホルモンをエサにして、HER2タンパクを持っていないタイプ
→ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌(ルミナールタイプ)
※ルミナールAやルミナールBのように分けて呼ばれる場合もあります。
②女性ホルモンをエサにして、HER2タンパクを持っているタイプ
→ホルモン受容体陽性HER2陽性乳癌(ルミナールHER2タイプ)
③女性ホルモンエサにせず、HER2タンパクを持っているタイプ
→ホルモン受容体陰性HER2陽性乳癌(HER2タイプ)
④女性ホルモンエサにせず、HER2タンパクを持っていないタイプ
→ホルモン受容体陰性HER2陰性乳癌(トリプルネガティブ乳癌)
この4つのタイプに応じて、全身治療が異なるのです。
全身治療の種類
一つ目は「内分泌療法」いわゆるホルモン治療/療法と呼ばれているものです。浸潤癌の中でも女性ホルモンをエサにするタイプ(①と②)に対して有効とされており、基本的には飲み薬を1日1回、手術後の後に5~10年続けることがほとんどです。乳癌のエサとなる女性ホルモンを減らしたり、エサの代わりになるものを投与して女性ホルモンが癌細胞にくっつく余裕をなくしたりすることで、癌細胞を兵糧攻めにする治療です。副作用として更年期症状や、骨密度の低下、場合によっては子宮内膜癌のリスクが上がるといわれていますが、生活の質が落ちるほどのものはほとんどなく、多くの方が無理なく続けられている治療です。
二つ目は「化学療法」いわゆる抗がん剤と呼ばれているものです。浸潤癌の中でも進行したものや再発リスクの高いタイプに行われます。HER2タンパクを持っているタイプ(②と③)やトリプルネガティブ乳癌(④)では抗がん剤治療が必要になることがほとんどです。体の中で入れ替わりの激しい細胞を攻撃する薬のため、癌細胞だけでなく、髪の毛や腸の粘膜、血液にも影響が出てしまいます。そのため、副作用として脱毛、食欲低下、吐き気、貧血、免疫力低下などがおこります。
三つ目は「分子標的薬治療」とくに抗HER2治療のことを指すことが多いです。HER2タンパクをたくさん持っている癌細胞を狙って攻撃するため、比較的副作用の少ない治療です。ただし、抗がん剤と併用することがほとんどのため、HER2タンパクを持っているタイプだから副作用が少ないというわけではありません。
最後の一つは「免疫チェックポイント阻害薬」というお薬です。免疫療法と呼ばれることもあります。これは、本来自分の細胞が持っている、”この身体の細胞です”という看板を、癌細胞が持ってしまっていることが多いため、その看板を取り除くことで、免疫細胞が癌細胞を攻撃するように仕向けるお薬です。抗がん剤と併用して非常に強い抗腫瘍効果を発揮しますが、実際の自分の細胞が持っている看板すらもとりあげてしまい、自分の体に対して免疫細胞が攻撃してしまう、「免疫関連有害事象(irAE)」という非常に厄介な副作用を起こすことがあります。
このように、乳癌のタイプに応じて、手術や放射線治療などの局所治療と、ホルモン療法や抗がん剤などの全身療法を組み合わせて行うのが、現在の乳癌治療の標準治療となります。
もっと詳しく知りたい!という方は、各治療の詳細について別記事でまとめていきますのでそちらをご覧ください。

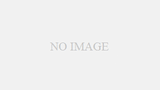
コメント